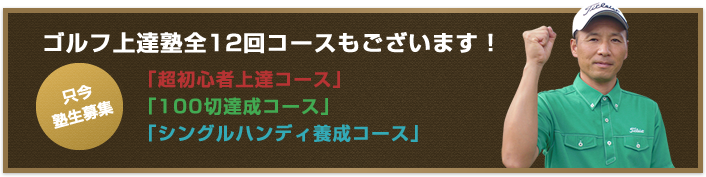レッスンブログ
グリーン上で立っていい場所悪い場所
パッティングは、大変集中力が必要です。
パッティングの際に、同伴者が不用意に動いたり、目に入ったりすると、
集中力の妨げになってしまいます。
グリーン上で順番待ちをするなら、どこに立っていればいいのでしょうか?
パッティングをしている人の真正面から、
■ 左右30度以内で
■ かつ、最低3メートル以上離れたところ
が理想です。
だいたい、気配が感じられない程の間隔だと考えれば良いでしょう。
一方、立っていて悪い場所は、
■ 打つ人の左右
つまりボールが転がるラインの延長線上です。
それと、打つ人の背後の2メートル以内(程度)もNGです。
4、5メートル以上離れていれば、まあOKでしょう。
知って得 「粋なマナーNo1」
パターが終わって、次のホールへ移動するときのエチケットです。
いま終わったカップから、グリーンの外に一番早く出られるところを探しましょう。
グリーンは、最もデリケートなエリアです。
なるべくグリーン面を踏んでいる時間や歩数を減らしたいものです。
ここまで細かく考えなくてもいいとは思います。
しかし、自己満足でもいいですから、グリーンをいたわる気持ちとして、実行してみてください。
次のホールへ遠回りになっても、いち早くグリーンから出て、そこから走りましょう。
そんなあなたの極上のマナーに、次のホールから、
ゴルフの女神もきっとあなたに微笑んでくれることでしょう。
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
「カントリークラブ」と「ゴルフクラブ」の違い
日本のゴルフ場は、
■ 「カントリークラブ」
■ 「ゴルフクラブ」
とに分かれますが、カントリークラブと、ゴルフクラブは、本質的には別のものです。
ゴルフクラブは、ゴルフを楽しむクラブ。
カントリークラブは、ゴルフ場に、テニス、乗馬、プールなどの施設を持ったクラブのことです。
アメリカの田園地帯に多く造られたことから、カントリークラブと呼ばれるようになったそうです。
参考文献 「月刊ゴルフレンジ」より
重いクラブと軽いクラブ、どちらがいいの?
「軽いクラブの方が速くスイングできる」
「重いクラブの方が軌道が安定する」
クラブの重い、軽いについては、諸説あるようです。
私たちレッスンの最前線にいるプロの意見も2つに分かれるようです。
軽いクラブ派は、
「重いとカラダが暴れるスイングになりやすい」
重いクラブ派は、
「手先でスイングするクセがつく」
と、どちらも一理あります。両者の中間を取ると、
「 18ホール、そんなに疲れずにプレーできて、スイングできる範囲で最も重いクラブ 」
で落ち着くのではないでしょうか。
しかし、それすら、よくわからないものです。
そんなゴルファーは、きっとキャリアも浅く、練習も少ないことでしょう。
それに、ふだん特に運動もしてないし、筋力もあるほうではない。
だとすれば、
「軽いなぁ~」
くらいの重さのクラブがいいと思いますよ。
ボールの使用期限、保存方法
ボールは生ものではないし、賞味期限はあるのか?とよく聞かれます。
プロレベルですと、はっきり性能が落ちる、とわかりますが、
たとえば、100ヤードの距離を狙って、2~3ヤードのズレを感じられるのがプロです。
アマチュアゴルファーの方ですと、現実、気にすることはない誤差でしょうか。
ただ、気持ちの問題ということもありますから、だいたい2、3ラウンドで交換するといいでしょう。
保存状態ですが、ボールは、熱と水には弱いのです。
真夏のトランクの中は、サウナ並みの熱さですから、
ボール内部のゴムの劣化が進みます。車のトランクに置きっぱなし、はNGですね。
水は、ボール表面のキズから、内部に吸収され、劣化が進んでいきます。
上級者や、プロゴルファーのボールの使い方は、
3ホールごとにローテーションするのが多いようです。
ちょっと休憩させて、といったところでしょうか。
ご参考にしてください。
意外と気づかないミスの原因
意外と気づかないミスに、
「メガネでのゴルフ」があります。
ふだんから、メガネを常用している人は当てはまらないかもです。
ゴルフをするときだけメガネをかける、という人は要注意です。
ふつう、メガネのフレームの真ん中でモノを見ようとするものでしょう。
バックスイングで、肩を回したとき、少なからず、顔も右に回ります。
このとき、ボールの上にフレームがかかり、ボールが見えにくくなりますね。
無意識に、ボールをよく見ようと、肩の回転を浅くしたり、
ダウンスイングのタイミングを速くしたりで、自分のタイミングを崩してしまいます。
あらかじめ、心の準備ができていると、一瞬のボールの見えにくさにも
無意識は対処してくれるかもしれません。
他によく聞くのが、メガネやサングラスをかけると、遠近感が狂うということです。
ちょっと慣れておく必要がありますね。
冬は、コンタクトの人は乾燥を嫌がって、メガネにしたりします。
ゴルフのときに、ちょっと覚えておいてみてください。
コースの距離表示を盲信するべからず
パー4やパー5のティーインググラウンドの距離表示。
意外と「長めに」サバをよんでいるホールがあります。
しかし、グリーンまでの残ヤード表示では、
そんなにサバをよんでいるホールはありません。
たとえば、「420ヤードパー4」の距離ですと、
420という距離を見ただけで力が入ってしまうものです。
一概には言えませんが、リゾートコースや、
格安のコースなどでは、サバを読んでいるコースがよくあります。
距離にビビらずに、ふつうにスイングしていきましょう。
仮に、しっかり距離があったとしても、力んで失敗してしまえば、
420ヤードが、「520ヤード」になりかねません。
月並みですが、常に”ふつうに”スイングしましょう。
パターの時、手袋は外すほうがいい??
ショットでは、ほぼ全員手袋をしていますが、
パターでは、外す人が多いようです。
しかし、中には外さずそのままパッティングしている人もいます。
トーナメントを観ていても、ほとんどの選手は外しています。
日本を代表する2大プロの青木功プロと、尾崎将司プロは、手袋は外しません。
パターは、大きな動きではないし、手元が滑るということはほとんどないでしょう。
手袋を外す理由を考えてみましょう。
パッティングは、繊細な距離感が必要なので、
素手の方が手先のタッチがパターに伝わりやすいことが第1に挙げられます。
また、ショットからパッティングに「場面」が変わり、
気持ちの切り替えのために手袋を外す、とも考えられます。
パターが苦手で、距離感なんてない、というゴルファーは、
特に外す必要もないかもしれません。
私自身、素手だと、かえって敏感になりすぎ、
緊張がパターに伝わってしまう気がして、手袋はしたままでパッティングをします。
結論として、外す外さないで、特に影響はなく、
気分次第でいい、というところでしょうか。
もちろん、外したほうが結果がいい人は
外してパッティングしてください。
コースで使うボールと練習場ボールの違い
コースで使うボールと、練習場で使うボールの違いをご存知でしょうか?
だいたい、練習場のボールは、1割くらいはコースボールよりも
飛距離が落ちるようです。
何度も何度も打たれていて、耐久性が弱っています。
また、1個あたりのコストもとても安く、
性能もコースボールと比較になりません。
しかし、最近のレンジボール(練習場ボール)は、
かなり性能がよくなりましたね。
10年ほど前までは、20%くらいは飛距離が落ちていましたが、
最近では、5~10%くらいでしょう。
練習場では、距離表示板が点在しますが、
練習場によって、ボールの飛距離ダウンに合わせて
距離表示を置いている場合と、
距離そのままで置いている場合があるようです。
かなりの腕前の人なら、打てば判ることでしょう。
アベレージゴルファーでは判らないかもしれません。
しかし、ボール自体が、コースボールと比較して、
5~10%程度しか変わらないのですから、
そんなに気にすることはないでしょう。
「打ち放題」と「1球いくら」
練習熱心なゴルファーの方は、
1球でもたくさん打ちたいことでしょう。
でも、私は「1球いくら¥」をおすすめします。
どうしても、練習が雑になり、
動作の確認もせずに、
球数さえ打てば練習した気分になってしまうからです。
それに、時間制限のある「打ち放題」は、
時間ばかり気にしていまい、内容のある練習ができません。
「たくさん打った!」という自己満足だけで、もしくは
悪い動きを徹底的に固めてしまうことにもなりかねません。
私は、
「練習場でたくさん球を打つ人は、コースでもたくさん球を打つことになる」
と考えています。
1球1球考えながら、動作をイメージしながら打てば、
1時間に100球がやっとでしょう。
「1球いくら¥」で、ていねいな練習をしていきましょう。
ブログカテゴリ
月別アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (91)
- 2022年7月 (15)
- 2020年5月 (8)
- 2020年4月 (1)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2017年12月 (7)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (1)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (22)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (6)
- 2015年12月 (23)
- 2013年9月 (2)
- 2012年12月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (1)
- 2011年10月 (14)
- 2011年9月 (1)
- 2011年7月 (55)